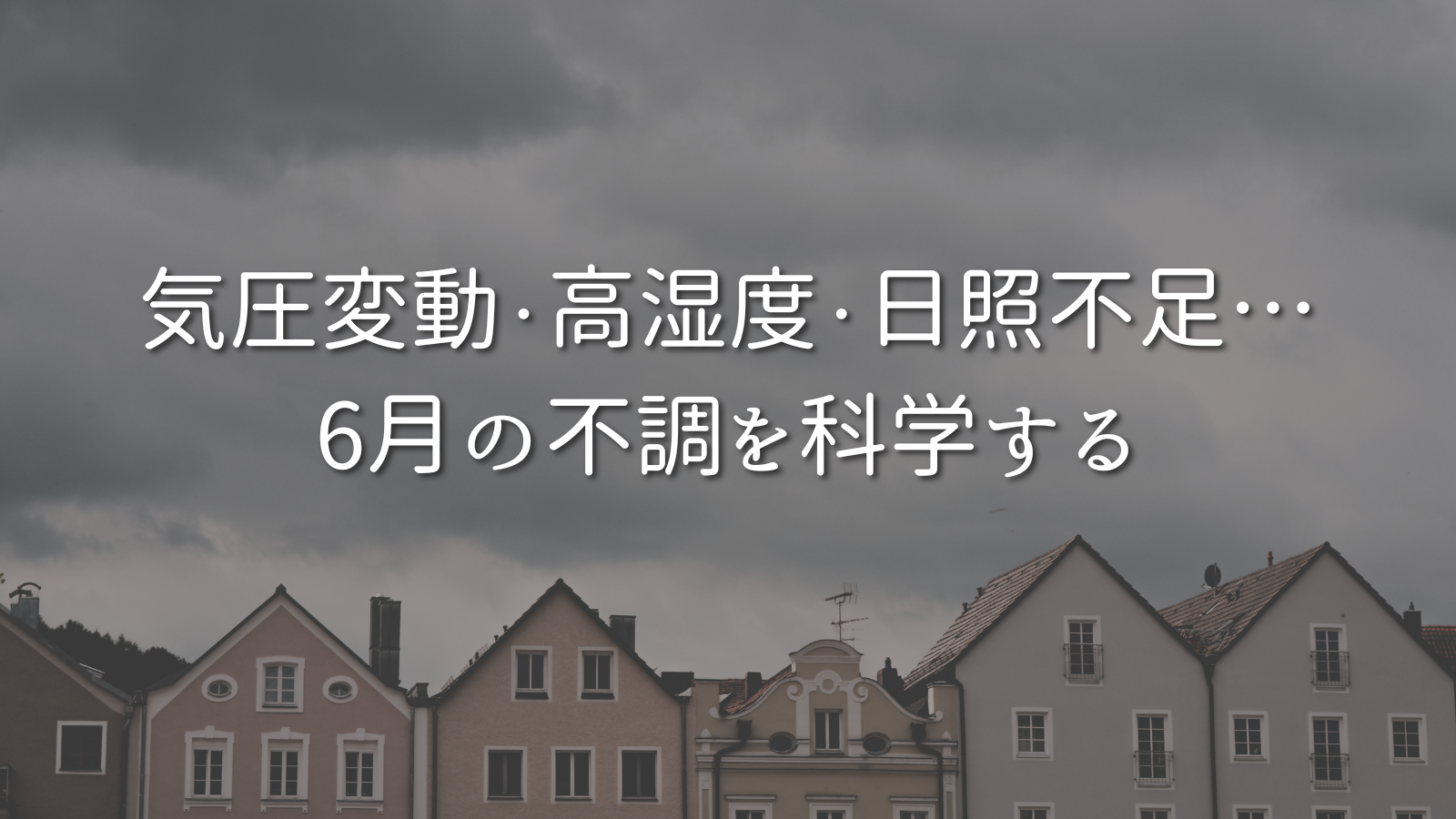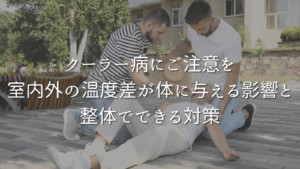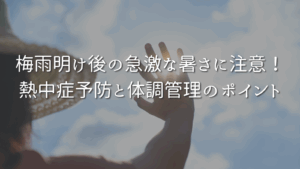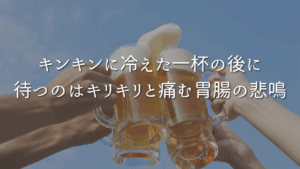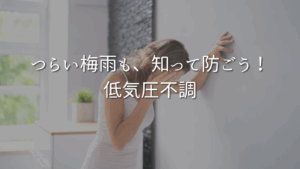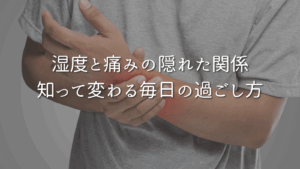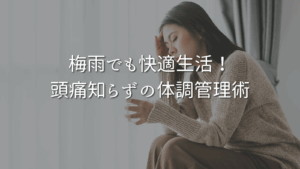6月病は梅雨の季節に見られる心身の不調を指し、気候の変化がその主な要因です。今回は6月病と気候の関係を詳しく説明します。
気候の影響
- 湿度の上昇: 梅雨時期である6月は湿度が高くなります。この高湿度により体温調節が難しくなり、身体にだるさや疲労感が生じやすくなります。また、体内の水分バランスが乱れ、集中力の低下を引き起こすことがあります。
- 気圧の変動: 梅雨時期は低気圧が頻繁に発生し、気圧が不安定になります。この気圧の変化は自律神経系、特に交感神経と副交感神経のバランスに影響を与え、頭痛、めまい、倦怠感などの症状を引き起こすことがあります。
- 日照時間の減少: 梅雨時期の日照時間の減少は、脳内の「幸せホルモン」であるセロトニンの分泌を低下させます。セロトニンは気分の安定に重要な役割を果たすため、その減少は気分の落ち込みや意欲の低下につながります。
心身への影響
- 疲労感やだるさ: 湿度や気圧の変化により、身体は疲れやすく、だるさを感じやすくなります。これは特に、長時間の屋内生活や運動不足と重なると悪化します。
- 精神的な不調: 環境の変化やストレスにより、心の健康も影響を受けます。イライラや不安感が増し、集中力が低下することがあります。
対策と予防法
- 規則正しい生活: 睡眠の質を高めるため、規則正しい生活を心がけましょう。特に梅雨時期は、朝の日光を積極的に取り入れることが効果的です。
- バランスの取れた食事: 栄養バランスの良い食事で免疫力を高め、体調を整えましょう。特にビタミンB群、C、ミネラルを含む食品を意識的に摂取することが大切です。
- 適度な運動: 軽い運動やストレッチで血行を促進し、心身をリフレッシュすることができます。
6月病は気候の変化と密接に関連していますが、適切な対策によってその影響を軽減できます。日常生活の見直しを通じて、心身の健康を保つことが重要です。
.png)